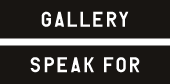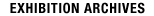中野敬久 | Hirohisa Nakano
音楽誌やファッション誌、CDジャケットなどで幅広く活躍中のフォトグラファー、中野敬久さん。映画や広告、音楽そしてもちろん写真にも精通し、被写体と響き合える個性が人気の秘密です。2006年に出会って、折に触れて撮影してきたギターロックバンド、ART-SCHOOLの写真をこのたび写真集にまとめ、GALLERY SPEAK FORにて初の写真展「Fade To Black」(2012年3月2日〜14日)を開催します。サブカルチャーにどっぷり浸かっていたインプット(吸収)過多の青春時代から、写真という方法に出会ってアウトプット(表現)へと目覚め、そして今に至るまで、ずっと自分を律しているのは「かっこよくあるべし」というロック幻想であり、フォトグラファー幻想だとのこと。どのようにしてその美意識を養ってきたのか、写真で伝えたいものとは何かを、中野さん自身の個人スタジオ「RIOT HOUSE」にて伺いました。
photo : Nobutaka Sato
自己表現を模索した留学時代
- ───
- 今のお仕事内容について教えてください。
- 中野敬久(以下、H):
- 音楽関係の撮影が多いですね。だいたい5割か6割の月もあると思います。CDジャケットや雑誌のための撮り下ろし。その他はファッションや広告撮影。雑誌のポートレート撮影です。被写体が男性か女性かを問わず、俳優さんでも、クールだったりシャープだったり、そういうキーワードをあげて撮影を依頼されることが非常に多いですね。自分で抱いているロック幻想みたいなものがあるんですよね。ミュージシャンに限らず表舞台に立っている人というのは、かっこよくなきゃいけないという固定観念でもあり、自分の中の脅迫観念にもなっているものがあって。そこを具現化するために僕のフィルターというのはあるのかなと思っています。ミュージシャンの一番かっこいいのは、ステージ上。それと同等のかっこよさをどうやって誌面などで形にしていくかというのは、撮る側にかかっていますから。
- ───
- フォトグラファーになったきっかけは?
- H:
- 父が広告代理店マンだったこともあり、広告が一番好きでした。中学生なのに「宣伝会議」や「ブレーン」を出版社から取り寄せて読んでいたり(笑)。また、映画も好きだったので「cut」「スタジオボイス」や「夜想」なんかも読んで、音楽もキャッチアップしていました。サブカルチャーど真ん中に浸っていましたね。ただ、インプットはそうやって十分なんですが、何をやったらいいか全く分かりませんでした。音楽を演奏してはいませんでしたが、90年代はじめ頃は渋谷系、アシッドジャズなどの流行期でしたから、DJになるのもいいなとイギリスへ。ロンドン近郊のノーリッジという街の学校に留学したんです。メディアを学ぶコースでしたが、はじめは英語が不得手だったので、単位が取りやすい実技科目ということで写真を学ぶことになりました。その時、暗室の中で浮かび上がる自分の表現というものに手応えを感じ、ロンドンで本格的にカレッジに入って暗室作業に没頭するようになったのです。
音楽へ引き寄せてくれたART-SCHOOL
- ───
- 日本に戻ってからフリーランスとして活動を始めたんですね?

- H:
- ロンドンでカレッジを出てすぐ、クリックスタジオという当時ロンドンで一番大きなスタジオでアシスタントとして働きました。ステファン・セドナウイ、アルバート・ワトソン、デヴィッド・シムズなどの現場を見られてたくさん吸収できたのですが、そのキャリアが役立って、日本に戻って間もなくグレン・ルッチフォードの東京での撮影現場にアシスタントで入り、その時の縁がつながってフリーランスとして活動を始めたんです。海外では、非常に狭い限られたエリアでのプロを求められますが、日本ではいろんな引き出しを求められるし、同じやり方ばかりでは通じない。また、海外のトップフォトグラファーたちは、ファッションを撮ってもポートレートを撮っても、人を撮ることをものすごく大事にしていると思うんです。その点、日本だと様々な人を撮らせてもらえることで幅広い経験も積める。自分のためになっていく気がして、そこが面白いところだと感じました。
- ───
- 「ART-SCHOOL」を長く撮影してきたのは、なぜですか?
- H:
- 2006年にCDジャケットを撮る仕事で呼ばれ、彼らのアーティスト写真を同時に撮ってくれ、ということで彼らと初めて出会いました。音楽的な面、歌っていることが自分に響いたバンドだったんです。僕自身、年間で数えたら結構な回数ライブを観に行きますし、それまで出会ったいろんなバンドが響かなかったわけではないのですが、ロック幻想が激しく、経験値も低いばかりに、ミュージシャンとは話しちゃいけないと圧倒的に信じ込んでいたんです。でもなぜか彼らと出会った時、自分のモードもぴたりとはまったのか、ちゃんとコミュニケーションをとりつつ撮れた。音楽の趣味も合ったんでしょうね。そのうち大きな会場だけではなく、地方の小さな会場にも撮りがてら遊びに行ったり、そこで撮ることで音楽と自分の距離がさらに近づいたり。それがまたさらに僕を音楽関係の仕事へ引き寄せてくれる結果になっていきました。今回は2011年末にメンバーが脱退し2人になってライブDVDもリリースされるということで、それをきっかけに僕としてもART-SCHOOLの写真を、初めての写真集にまとめようと思いました。僕はライブの記録を撮れるカメラマンではないんです。写真史的にもドキュメンタリーがもともと好きですし、今回の写真集もライブドキュメンタリーだと思っているんです。演奏自体をかっこよく撮るということではなく、彼らの物語を写真で伝えられればいいと思っています。
空気感をすくいあげる写真を
- ───
- 彼らの「物語」、どんな物語でしょうか?
- H:
- 写真集をめくっていく時に響く物語、というか。彼らが鳴らしている音ひとつひとつによる物語なのかなと感じています。僕はやはり人を撮るフォトグラファーだと思っていますが、モノを撮っても人を感じさせたいんです。今回もミュージシャンがステージでギターをかき鳴らす瞬間のかっこよさを、どのように写真に置き換えていくかを考えていました。ライブでは、ただの照明の光線やアンプ、セットリストだけを撮ったり、スタジオでもギターのクローズアップなどで、空気感のようなものを象徴できたらと。今回の写真集も写真展も、ぜひ音楽をよく知らない人たちにたくさん見てもらいたいですね。メディアがインティマシー(親密さ)を得やすく進化したがゆえに、ロック幻想が失われて久しいと思うんですが、演奏する側と観る側の距離感が一定程度あることで、むしろ伝わることもある。それをもう一度共有して、ミュージシャンってかっこいいなと思ってもらえたらいいなと思っています。
- ───
- 今後の目標や、こういう撮影をしていきたいという方向性は?
- H:
- ロック幻想を、フォトグラファー幻想に置き換えても同じことが言えるのかも知れません。90年代にマリオ・ソレンティやデヴィッド・シムズ、グレン・ルッチフォードなどがファッション、音楽やエンターテインメントを結びつけるような活躍をして、そこから停まっている感じがするじゃないですか。それ以降も重要なエポックはあったのですが、日本人が洋楽をあまり聴かなくなったのと同じで、まるで関係ない話になっています。写真表現でも、ブログみたいな表現の写真、インスタグラムみたいなものは発達したと思うけど、やはり技術も必要だし、空気感を感じ取る力を持ったフォトグラファーも育てていくべきで、僕が言うのもおこがましいですが、そういうことも考えてしまいますね。今回の写真集でどういう反響があるのか分かりませんが、数年後、僕のようにふとした瞬間に写真を始める次の世代の子が、こういうことをやりたいと思うものは置いておいてあげたいなと思いますね。

中野敬久(フォトグラファー)
1993年に渡英し、ロンドン・カレッジ・オブ・プリンティングにて写真・映像を学ぶ。撮影スタジオにてアシスタントを経験した後、帰国。99年、グレン・ルッチフォード氏のアシストをきっかけにフリーランス・フォトグラファーとして独立した。ファッション誌、音楽誌、カルチャー誌などのファッションストーリーや、国内外のアーティストたちのポートレート、CDジャケット、広告などを幅広く手がけている。2011年、世田谷区下馬に自身のスタジオ「RIOT HOUSE」をオープンした。
http://www.hirohisanakano.com/
「Fade To Black」展についてはこちら
http://blog.galleryspeakfor.com/?eid=568
中野敬久さんの商品はこちら
http://www.galleryspeakfor.com/?mode=grp&gid=278845